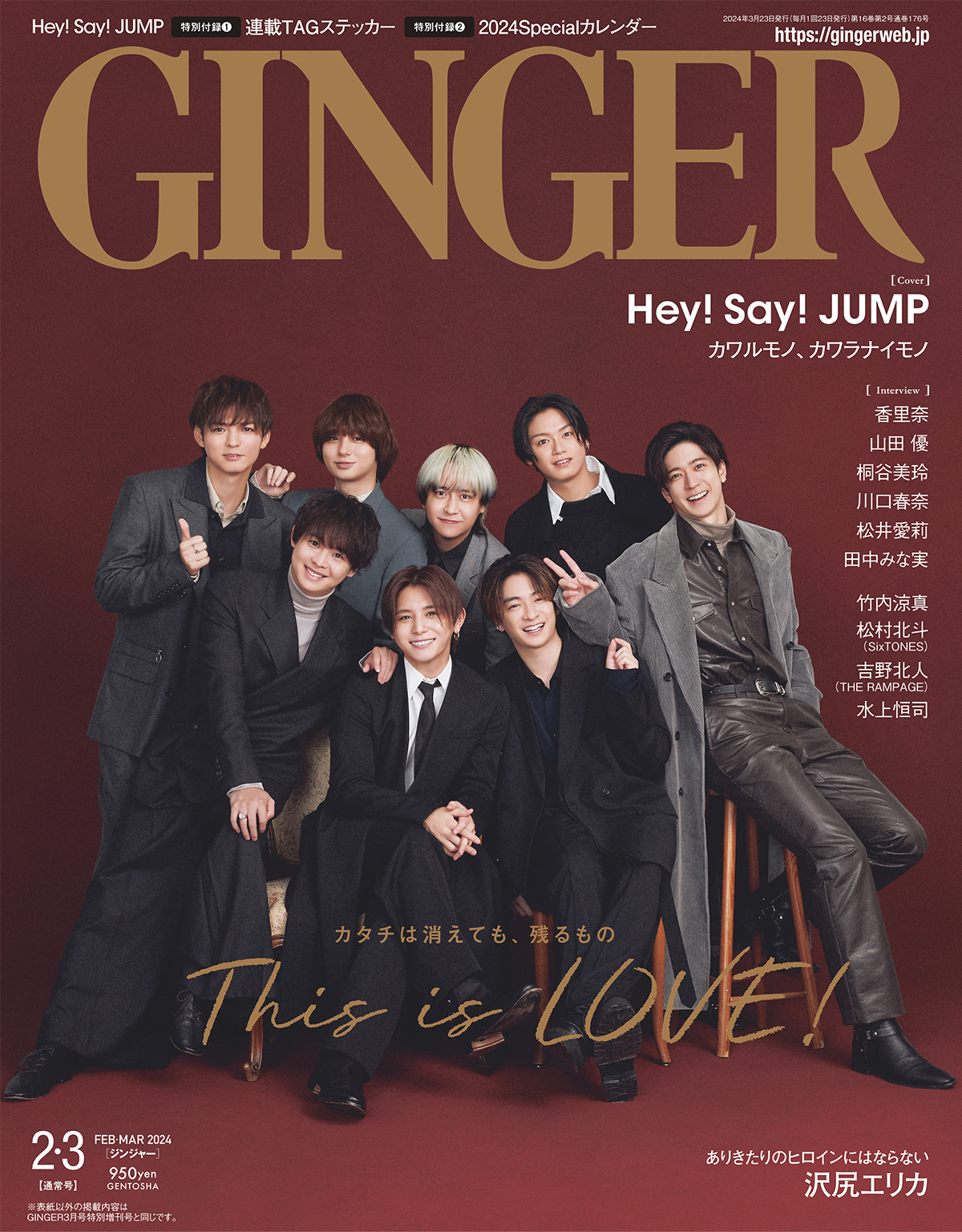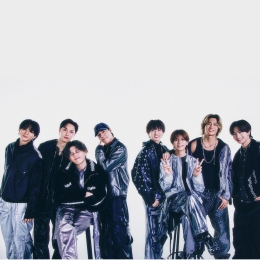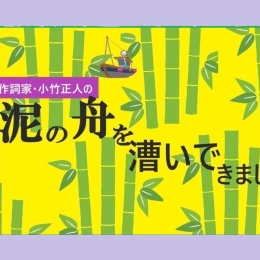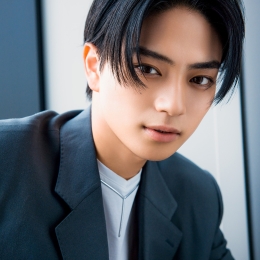“わたしの心地よさ”を基準に行動することが、ウェルビーイングに生きるカギになる。そのために、もっと自分自身を知る=自分のトリセツを手に入れませんか? 保健学博士の島田恭子さんがナビゲート。【連載「自分学 わたしのトリセツ」vol.27】
感情知能(EQ)と集中力の深いい~関係

スマホ片手に私たちは、いつも忙しい日々を送っています。仕事(勉強)のときもお休みのときも、SNSの通知に気を取られ、「長時間集中なんて難しい!」という方も多いのではないでしょうか。「ついつい気が散ってしまう、どうすれば仕事(や勉強)に集中できるんだろう」「なぜあの人は、あんなに没頭できるんだろうか」と不思議に思ったこと、ありませんか?
前回の連載では、知能とも学力とも違う、でも私たちにとってとても大切な「感情知能(EQ)」の存在についてご紹介しました。なんとこのEQ、私たちの”集中力”や”生産性”にも深く関係していることがわかっているんです。
感情と集中力

感情と集中力、一見関係なさそうな2つですが、どうつながっているのでしょう。おさらいですがEQは、主にこれらの要素で成り立っていました。
- 自己認識:自分の感情に気づく能力
- 自己制御:感情をコントロールする能力
- 動機づけ:ポジティブな姿勢で目標に向かって努力できる
- 対人的スキル:他人と円滑な関係を築くことができる
集中力とのつながりでいうと、特に上の3つと深く関わっています。
1.自己認識:集中の妨げとなる感情を知る
私たちが集中できないとき、私たちどんな思いを抱えているでしょう。
例えば――
- 不安:「この仕事、うまくできるだろうか…」
- 退屈:「この作業に意味があるのだろうか…」
- 焦り:「時間が足りない、急がなくては…」
- 怒り:「さっきの会議での発言、モヤモヤする…」
これらの感情に気づかないまま作業を続けると、私たちの注意はおのずとその感情に引っ張られ、表面的な集中しかできない状態となります。
もし私たちに、感情に対する「メタ認知的気づき」(自分の思考や感情をナナメ上から客観的に観察する能力)があったら…? 「今わたし、焦っているな」と冷静に気づくことで、その感情を脇に置ける、次のステージに進むことができるのです。
2.自己制御:感情の波をサーフィンする
感情に気づいたら、次はそれをコントロールするステージ。ここでいうコントロールとは、感情を抑え込むことではなく、波に乗るようにうまく対処する、といったイメージです。
たとえば、締め切りが迫った企画書を書いているとき…。「間に合わないかも」という不安が湧いてきますよね。EQが低いとその不安に飲み込まれ、思考が混乱します。EQが高いと「今は不安を感じているけれど、それはいったん脇に置いて、まずは目の前の1行目を書くことに集中してみよう」と、意識的に注意をコントロールできるのです。
3.動機づけ:内発的なモチベーションを高める
集中力の質は、その活動に対する私たちの感情的なつながりに大きく左右されます。もちろんポジティブな感情のほうが、そうでない感情よりも、よりパフォーマンスを発揮できますよね。「楽しい」「わくわく」「熱意ある」「面白い」「充たされている」状態だと、高い集中力を感じやすいし、パフォーマンスが高くなりますよね。自分にとって意味のある目標を設定し、その過程を楽しむ力は、深い集中状態を生み出す重要な要素です。
たとえば単調なデータ入力の仕事であっても、「このデータが整理されることで、どんな価値が生まれるか」「いかにこれを正確に、早くできるかやってみよう」「自分の貢献がどう役立つか」を意識することで、作業へのポジティブな感情的が生まれ、より深く集中できるようになります。
こうして、外部の刺激や内なる感情の波に振り回されることなく、意識的に自分の注意力を向けたい方へ向けることができるようになります。これが「ゾーン」= 時間を忘れるほど没頭できる状態——の入り口となります。
集中力への挑戦

私たちの脳は、新しい情報や刺激に反応するようにできています。スマホやPCの通知、嗜好に合った楽しいショート動画などは、わたしたちの脳にとって、なかなか無視しづらい刺激ですよね。またSNSに投稿すると「いいね」がもらえ、それが即時的な報酬となって、脳はまたその刺激を求めるようになっていきます。
現代のこんな環境のなかで、深い集中を得るのって、なかなか大変そうです。そこで意識的な感情のコントロールが大事になってきます。たとえばこんな感じです。
(1)スマホを見たい衝動が湧いたとき、それを「感情的な欲求」として認識する
(2)その欲求に単に反応するのではなく、「今は集中したい」という意図を思い出す
(3)衝動を一時的に保留し、目の前の作業に戻る
感情のマネジメントができると、目の前の作業に戻ることができる。これがまさにEQの実践です。自分の感情を知り、自分の意図に沿った行動を選択する力をつける訓練ですね。
EQと集中力を高める、おすすめ習慣8選

では次に、日常生活のなかでEQと集中力を同時に高めるのによい習慣を、一緒に考えてみましょう! 感情を整えるのも、集中力を高めるのも、どちらも難しいスキルですが、そのつながりが意識できるだけで、ハードルが下がり、お得感が増しますね。
おすすめ習慣1:自分の感情状態を知る
なにか作業を始める時は、自分の感情状態をチェックしましょう。いつも「今、どんな気持ち?」と自問し、もし不安や焦り、イライラといったネガティブな感情があれば、それを認識します。
やってみよう
・作業前に30秒、目を閉じ、深呼吸をしながら感情にイシキを向ける
・「今の私の気持ちは〇〇だな」と言葉にしてみる
・ネガティブな感情があれば「この感情は今の私の一部だけど、すべてではない」と認識する
おすすめ習慣2:環境を整える
私たちの脳は環境からの影響を強く受けます。集中力を高めるためには、外部からの刺激をできるだけ減らしたいもの。まずはまわりを見回してみて。
やってみよう
・スマホは別の部屋に置くか、「おやすみモード」に設定
・作業スペースは整理整頓、視覚的な乱雑さを減らす
・自分が集中できる環境音(静けさ、自然音、カフェの雑音など)を見つけてみて
・「これから〇分、集中時間」と宣言、周囲の人に協力を求める
・スクリーンタイムを設定。ついつい見てしまう動画の流し見を制限する
おすすめ習慣3:感情コントロールのアイデア
感情の調整に有効なのは「意図的な注意のシフト」。ネガティブな感情に囚われたら、「今、このタスクの面白い部分は何だろう?」と注意をシフトさせる練習をしてみてくださいね。
やってみよう
・状況の捉え方を変えてみる(例「大変な課題」→「成長の機会」:認知再構成といいます)
・深呼吸を5回すると、交感神経の興奮が鎮まりますよ
・感情が高ぶったら、すっとその場を離れて冷静になる時間を(タイムアウト)
・「それでも」を口ぐせに(例「不安だけど、それでも一歩進める」)
おすすめ習慣4:単一タスクを意識する
”タイパ”が大好きな私たち。でも実は「マルチタスク」は脳にとって大きな負担。EQの土台となる前頭前皮質の機能を低下させます。集中力のためには、1つのことだけに意識を向ける方がよさそうです。
やってみよう
・取り組むタスクを明確に具体的に定義(例:「企画書を書く」→「企画書の導入部分を30分で書く」など)
・PCでは今使っていないタブやアプリをすべて閉じる
・ポモドーロ・テクニック(25分集中→5分休憩)を活用する(私もアプリで始めました!)
・作業中別のことが思い浮かんだら、メモに書き留めて後で対応する

おすすめ習慣5:休憩、大事!
集中は、脳にとっては疲労です。適切な休憩を取ることで、感情のバランスを取り戻し、脳の疲労を癒やすことができます。
やってみよう
・休憩時間は、スマホ、PC画面(スクリーン)から離れる
・遠くを見る(窓の外を眺める、植物を見る、空を見上げる)時間をつくる
・数分間、ゆっくり体を伸ばしたり、軽い体操をする
・深呼吸を5回行い、意識的に体の緊張を緩める
おすすめ習慣6:深い呼吸と身体感覚への気づき
呼吸は、感情と集中力をつなぐ大事な架け橋です。とくに深い呼吸は副交感神経を活性化し、感情のバランスを整えます。
やってみよう
・1日は深呼吸で始まり、深呼吸で終わる。起きてまず10回、寝る前10回の深呼吸を
・作業の合間に「呼吸休憩」を取る(2分間、呼吸だけに集中する)
・座り方や姿勢が呼吸と気分に与える影響に注意を払ってみましょう
おすすめ習慣7:デジタル・デトックスの時間
私たちの毎日はいわば”常に接続された状態”。ONが続くと私たちの注意力と感情調整能力は摩耗します。今の時代、どれも難しいかもしれませんが、意識的にテクノロジーから離れる時間(OFF)をつくるのがおすすめです。
やってみよう
・毎日30分の「スクリーンフリー・タイム」をつくる
・仕事中はデバイスを使わない、と約束する
・就寝前1時間はスクリーンを見ない習慣を
・週末に半日だけ、「デジタルデトックス」を実践する
おすすめ習慣8:「今、ここ」への意識的な注目
この連載でもご紹介しているマインドフルネスの実践は、EQと集中力両方を高める効果があります。
やってみよう
・日常の活動(食べる、歩く、お風呂など)を”意識的に味わう”(セーバリングの回ご参照)
・私たちの五感を使って「”いま”、”ここ”」の体験に意識を向け、注目する
・何か(電車、エレベーター、人)を待つ時間を自分のなかで「気づきの練習時間」として活用する
EQが導く「最高の集中状態」

なにかと誘惑が多い現代。集中力をつけるのは難しそうに思えますが、良いパフォーマンス状態は、わたしたちの感情とのバランスのなかで生まれる、ということがお分かりいただけたと思います。
もう一度おさらいすると、EQの高い人は
- 自分の感情状態に敏感に気づき、
- 注意を妨げる感情をうまく調整し、
- 作業に対する前向きな感情的つながりをつくり出し、
- 環境からの影響を適切に管理することができる
ってことですよね。これが少しずつできるようになると、現代社会の様々な誘惑や刺激のなかでも、自分の意図した方向に注意を向け、良い感じの集中状態(「ゾーン」といわれます。よくスポーツ選手などが集中・没頭した状態として表現される言葉としても有名ですよね)を体験できるようになるようです。それは単に仕事や学習の生産性が上がる、ということだけではなく、私たちの日々がより充実し、より深い満足感に満ちたものになる、ということなのです。感情知能と集中力は、幸せな人生を歩むための、大事な2つの車輪のようなものかもしれませんね。
島田恭子(しまだきょうこ)
予防医学者・保健学博士。医学や心理学の知見を、女性のウェルビーイングに役立てたいと活動中。(社)ココロバランス研究所代表。
https://customer-harassment.org/kyokoshimada/