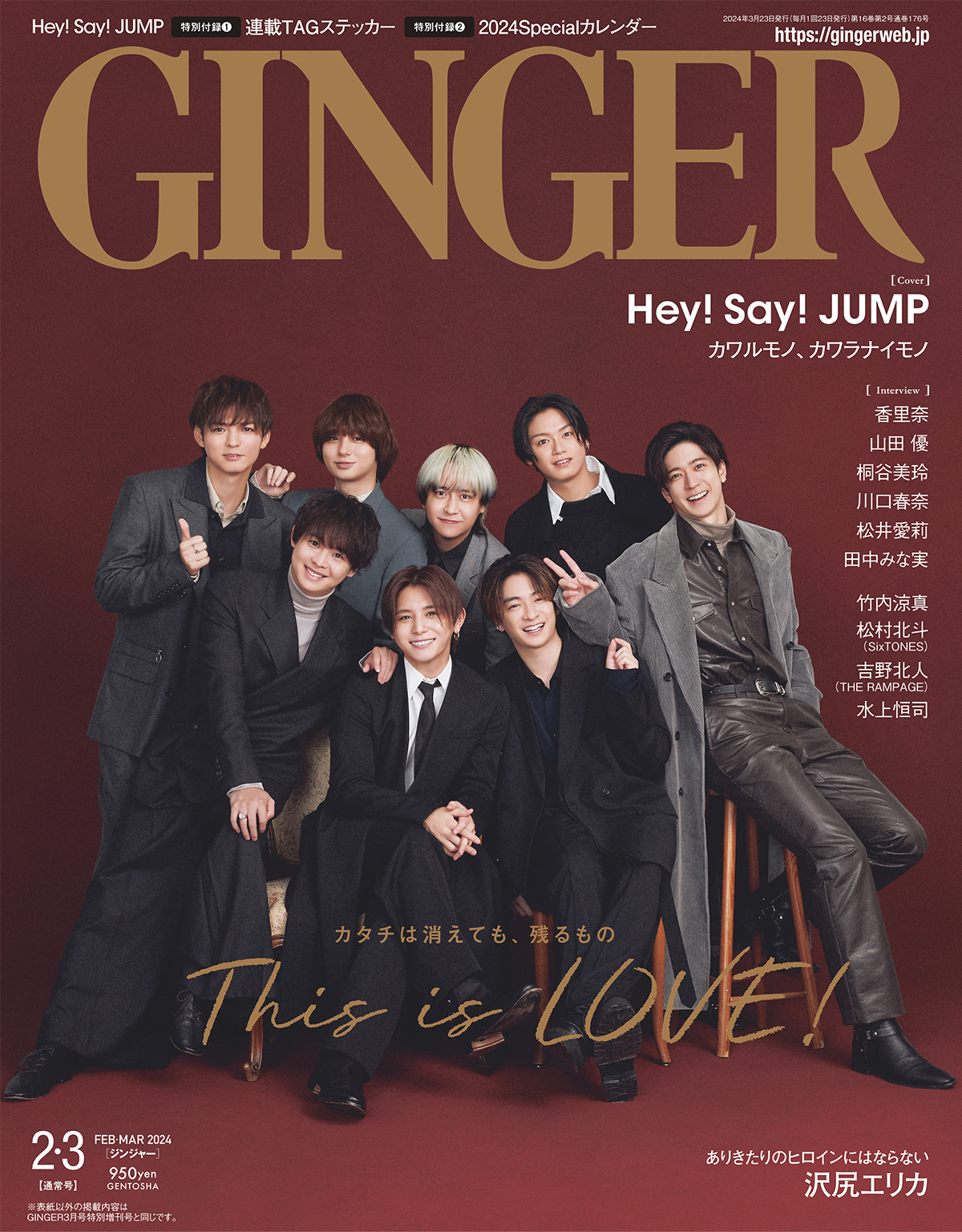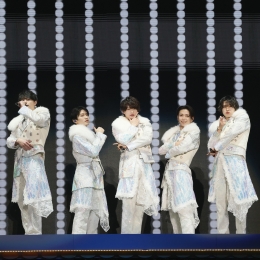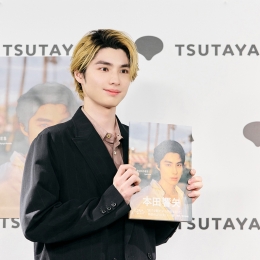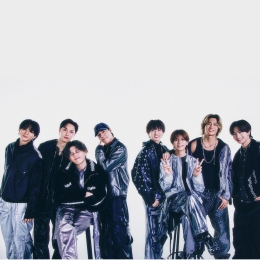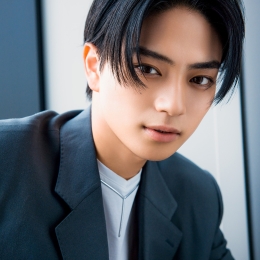“わたしの心地よさ”を基準に行動することが、ウェルビーイングに生きるカギになる。そのために、もっと自分自身を知る=自分のトリセツを手に入れませんか? 保健学博士の島田恭子さんがナビゲート。【連載「自分学 わたしのトリセツ」vol.34】
私たちがつい見失ってしまいがちなもの

先日母の家に行ったときのことです。
母がずっと私に何かを話してました。
私はキーボードの打つ手を止めることもなく、顔も上げず「うんうん」って生返事してたんです。
ふと気づいて顔を上げると、何かを諦めたような、寂しそうな母の顔。
ハッとしました。
(あ……私、いま、お母さんの顔、全然見てなかったな)
母の寂しそうな顔が頭から離れなかったその夜、久しぶりにある本を読み返してみました。
その名も「ユマニチュード」。響きだけ聞けば、南仏のオーガニックコスメか、新しいハーブティーみたいですが、実は、フランス生まれの認知症ケア。初めてユマニチュードを知ったとき、「この考え方、認知症の人だけじゃなくて、職場、友達、家族、どんな人とも温かい関係になれる魔法だな」って思ったことを思い出したんです。
何年か越しにそっと開いてみました。
やっぱりそこには、あまりにも優しく、そしてつい忘れがちな「コミュニケーションの基本原理」が書かれていました。
ユマニチュードの哲学は、こうです。
「たとえ相手が認知症で、言葉を失い、反応が薄くても、
『あなたは大切な人間だ』というメッセージを、
五感のすべてを使って伝え続ける」
現代の私たちが、忙しさや焦りのなかで、つい見失ってしまいがちなもの。
私たちは忙しさのなか、タイパ・効率を重視し、同時並行でいろんなことをこなしている。スマホ片手に「言わなくてもわかるでしょ」とばかりに言葉を端折り、視線を合わせるのをサボり、「正しさ」や「速さ」を優先し、相手の言葉を遮り、おたがいの気持ちをゆっくりと受け止め合う時間を省いてしまう…。
私が、母の「顔」ではなく、PCの「画面」を見ていたとき。
私が彼女に伝えていたのは「あなたを大切に思っている」ではなく、「あなたより仕事が大切」という、冷たいメッセージだったかもしれません。
そんな自戒を込めながら…。今回紹介する「ユマニチュード」には、こんな私たちのすれ違いがちな日常を「ほわほわ」に変える、4つの優しい魔法があるんですよ。

1979年、ユマニチュードを開発したフランスのイヴ・ジネストさんとロゼット・マレスコッティさん。体育教師として病院で、腰痛予防を教えていました。
ある日、看護師さんが黙々と男性患者さんの体を拭いていました。「この方は重度の半身麻痺で、全く反応がないんです」、男性は目を閉じて静かにしていました。そんな男性にジネストさん、ある方法で声をかけます。
すると、男性。ゆっくり目を開け、手を貸したら自分で起き上がり、なんと車椅子に座ったんです。
看護師さん一同:「えええええええ!?」
---人間って、声をかけ、目を合わせてもらえると、こんなにも反応するんだ。当たり前すぎて、誰も気づいていなかったこと。これがユマニチュードの始まりでした。
「見る」「話す」「触れる」「立つ」〜4つの小さな魔法
ユマニチュードには、驚くほどシンプルで、でも優しい4つの魔法があります。
優しい魔法 その1:【見る】
当たり前、と思いますよね。でも、ユマニチュードの「見る」は、解像度が違うんです。
「真正面から、同じ目の高さで、長く見つめる」。
これが「あなたの存在を認めています」という最強のメッセージになるからです。
家族と話すとき、スマホを見ていませんか?
友人と話すとき、カフェのメニューを見ながら返事をしていませんか?
まずは、その手元のスマホをしまい、メニューを閉じ、同じ高さに座り、目を見つめる。
たった数秒。
その数秒が「私は、あなたと話したい」という温かく優しいサインになるのです。
優しい魔法 その2:【話す】
ユマニチュードでは、相手から返事がなくても「背中、洗いますね」「気持ちいいですね」と、今やっていることをポジティブな言葉で「実況中継」し続けます(オートフィードバック)。
これを応用し「命令や否定ではなく、優しく穏やかに、肯定的な言葉をかけ続ける」こと。
たとえば「なんでできてないの?(否定)」とか「早くこれやって!(命令)」。ーーこれは、相手を焦らせたり、不安にさせたりするメッセージになりますね。
「お、資料、頑張ってくれてるね(肯定)」、「いいね。この部分、私ならこうするかも(提案)」ーーこれは、相手を安心させるメッセージになりますよね。
優しい魔法 その3:【触れる】
ユマニチュードでは「つかむ(Grab)」のではなく、広く、柔らかく、ゆっくりと「触れる」。「あなたは大切にされてる」が手のひらから伝わるように、赤ちゃんを包み込むみたいに。
「つかむ」のは、相手を「モノ」としてコントロールしようとしているみたい。
その代わりに「広い面で」「優しく」「ゆっくりと」をイシキします。
これ、私たちの日常でも、心当たりがあるかも。
「ちょっと来て!」と相手の腕を急に「つかむ」。
会議で、相手の発言を「つかむ」ように遮る。
相手の時間を「つかむ」ように、いきなり本題を叩きつける。
全部、相手をコントロールしようとする行為。
自分が焦っているときほど私たちは、相手の心を「つかんで」しまおうとします。
そうじゃなくて。
まず、相手の心に「そっと触れる」優しさで、「今、ちょっといい?」と聞く。
相手の心を「つかむ」のではなく、そっと「ノックする」。
それだけで、相手の聞く姿勢はガラリと変わりそうです。
優しい魔法 その4:【立つ】
これが一番「じわっと」くる魔法。
人間は「立つ」存在である、という哲学から、介護現場では「寝たきりにしない」ことを支援します。
私たちの日常におきかえると「相手のできることを応援し、自分で決める力を信じる」。「こうした方がいいに決まってる」と正解を押し付けると、相手が自分で悩み、考え、決断する力を、奪ってしまうことに。
これは、相手から「自律性(Autonomy:自分の人生は自分で決めている、というとても大切なコントロール感」)」を、失わせる行為となるのです。私たちは誰かに「決めつけられた」瞬間、無力感を覚え、やる気を失い、心を閉ざすもの。たとえその答えが「正解」だったとしてもです。
「あなたは、どうしたい?」
「あなたはどう感じてる?」
相手が自ら考え、ハンドルを握り、自分の足で「立つ」のを応援する。それが本当の意味で「相手をリスペクトする」ということではないでしょうか。

ある介護施設でユマニチュードを導入したら、認知症の方への向精神薬が4年で40%も減った、という症例報告があります。薬じゃなくて、目を合わせて、話しかけ、触れるだけで。
さて、私事ですが、次に母が話したそうに近づいてきたならば…。
私は、スマホをしまい、PCをパタンと閉じます(1:見る)。
そして正面に向き直り、「なあに?」と声をかけるでしょう(2:話す)。
母の話は正直いつも、5分で終わる内容を30分かけて話すような、まとまりのないもの。
そして「あぁ、この結論なら、こう言ってあげればいい!」と、口から出そうになる「正論」をぐっとこらえ、「うんうん、そう感じたんだね」と、肩に手を当ててあげようとおもいます(3:触れる)。
そして、最後にこうたずねます。
「お母さん自身は、どうしたいと思ってる?」って。(4:立つ)
私がやるべきなのは、話も聞かず「正解」を伝えることではなく、ただ、優しい気持ちでそばに寄り添うことだけ。私たちの日常で必要なのは、おおげさな「解決策」より、お互いが「大切にし合っている」と実感できる小さな瞬間の積み重ねなのです。
その瞬間を実感できる魔法が、この「見る・話す・触れる・立つ」こと。
さあ、まずはスマホを置いて、隣にいる人(親でも、友人でも、同僚でも、家族でも)の目を、優しい気持ちで見つめてみませんか?
参考文献
『ユマニチュード入門』2014 イヴ・ジネスト, ロゼット・マレスコッティ著 本田 美和子翻訳 医学書院
Honda, M., Kobayashi, R., & Zin, M. (2016). Effects of Humanitude-based comprehensive care on agitation and antipsychotic drug use in dementia. Psychogeriatrics, 16(1), 71–78. https://doi.org/10.1111/psyg.12130
島田恭子(しまだきょうこ)
予防医学者・保健学博士。医学や心理学の知見を、女性のウェルビーイングに役立てたいと活動中。(社)ココロバランス研究所代表。最新著書『心が疲れたらセルフケア』が好評発売中。ストレスなく心の疲れを取り、元気を取り戻すための50の方法を紹介。
https://customer-harassment.org/kyokoshimada/