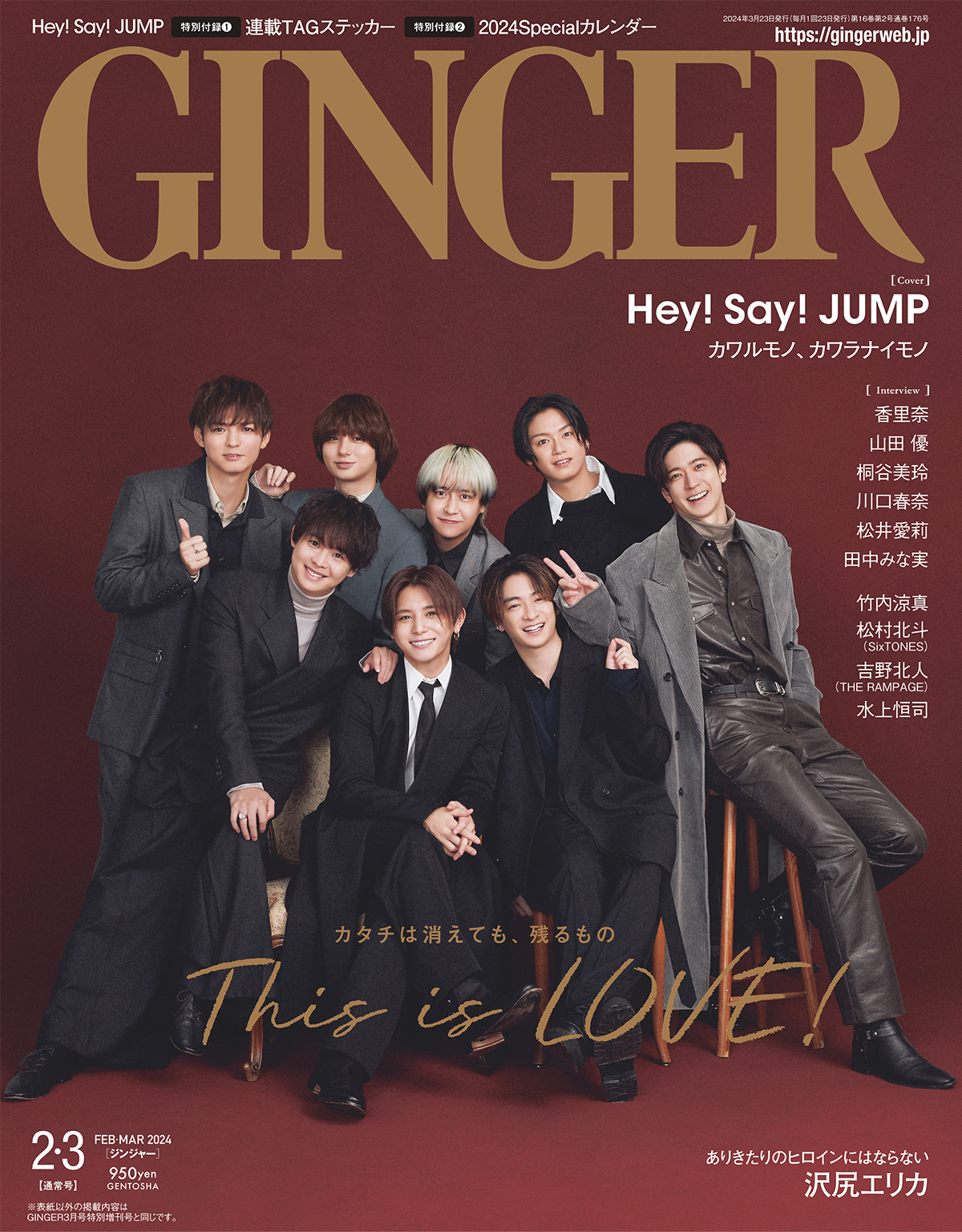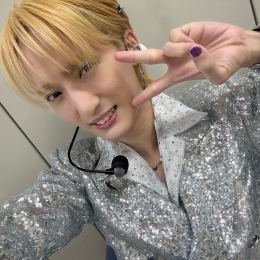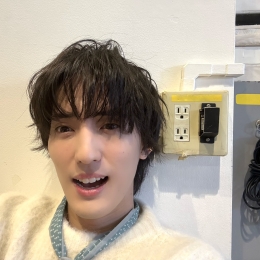スタイリスト青木貴子さんによる、素敵な人に一歩近づく生き方指南。こんな時代だからこそ、前を向いて歩いていくためのヒントをお届けします。
「伝えたい」が凝縮されたスピーチの強さ

先日、被爆80年となった広島市で広島平和記念式典が行われ、地元の小学生による「平和への誓い」が読み上げられました。
今回の子供代表はともに市内の小学6年生の佐々木駿さんと関口千恵璃さん。佐々木さんは小学校2年生のときから平和記念公園で海外から訪れた外国人に被爆の歴史を伝えるボランティアガイドをしています。彼の曽祖母は被爆者、がんを煩い亡くなったそう。そしてウクライナから避難してきた女の子の友人がいるという関口さん。そんな実体験から、2人はともに戦争を身近なものとして受け止め、食い止めるべき対象と心から思っています。
戦争は終わってもなお被害者は苦しみ続け、その終わりはないことを実感している佐々木さんは「二度と核兵器を使って欲しくない。戦争を止める助けになるよう平和への架け橋になりたい」。父親を母国に残し日本に避難してきた友人に接し、家族を離れ離れにし日常を壊したのは戦争だという思いに至った関口さんは「世界の主導者に争いではなく違いを認め、話し合って解決する大切さに気付いてもらいたい」とそれぞれ心のうちを語っています。そんな彼らの読み上げた「平和への誓い」は心にずんと響くとてもとても大切な思いが込められていました。

「平和について関心をもつこと。多様性を認め、相手のことを理解しようとすること。一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば、傷つき、悲しい思いをする人がいなくなるはずです。周りの人たちのために、ほんの少し行動することが、いずれ世界の平和につながるのではないでしょうか」
これは戦争に限ったことではなく、日常の諍いをなくすことができる重要な心持ちだなぁと思いました。日々の小さな積み重ねが戦いを回避する大きな力になる、それは真理だと思います。
「One voice. たとえ一つの声でも、学んだ事実に思いを込めて伝えれば、変化をもたらすことができるはずです。大人だけではなく、こどもである私たちも平和のために行動することできます」
わかっちゃいるけど、って言いながら平和のための心がけを実践しないひとは実は何もわかっちゃいないってことですよね。小学6年生である2人からの平和への呼びかけ。「子どもである私たちも行動することができます」…この言葉を聞いて、大人の私たちも本気で行動しなくっちゃね、とあらためて私は平和のために何をしているんだろうと考えさせられました。そして子ども代表スピーチ後の石破首相のご挨拶スピーチの、平和への想いを伝える言葉の選び方にも心が動きました。
考えさせられる、心が動く、そうスピーチって威力があります。スピーチはその人が届けたい、本当の言葉(想い)だから深く伝わる。その言葉たちは、何度も何度も推敲して集められたエキス。だから尊く素晴らしい、心に迫る言葉になるのです。
今回平和式典でのスピーチを聴いて、スピーチの持つ力や魅力についても気になって、過去の有名なスピーチをいくつか読んだり聴いたりしてみました。絶賛されているスピーチは実に心に響くものが数多あって、はっとさせられるものや考えを深く巡らさせてくれるもの、共感するものなど、心の琴線に触れるものに多く出合えました。

誰かが、心底伝えようと思っている言葉。その真摯な思いに耳を傾けると何らかの感情が湧き上がってきます。助けられる思いを持つことも、勇気がみなぎってくることもある。良いスピーチに触れると、思いがぐるぐる巡るので思考力を磨くことにもつながります。今は調べれば簡単に先人たちの名スピーチを聴くことも観ることも出来ます。たった数分で本を一冊読んだような感銘を受けることもあるかもしれません。
そして自分でスピーチを書いてみるもの面白いのでは? 何を訴えたいのかを深掘ってみると、自分が何に興味があって、何を主張したいのかに気が付きます。普段は無意識下にあった思いがむくむくと湧き上がって、自分発見もできるかもしれません。自分自身が持っている思考や思想について一生懸命考える機会って意外とないですよね。忙しいから立ち止まって深く考えることもなく毎日を過ごしている。そういったひと、少なくない気がします。
自分でスピーチを書くのはハードルが高いかもしれないので、まずは興味のある分野のスピーチを見聞きしてみては? 感動は心の栄養といいます。スピーチで心の栄養チャージ、移動時間の合間に心に潤いを与えてみる。ちょっとでも、とっても有意義な時間の使い方かと思います。