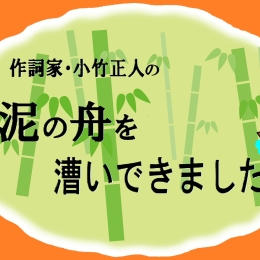令和の清少納言を目指すべく、独り言のようなエッセイを脚本家・生方美久さんがお届け。 生方さんが紡ぐ文章のあたたかさに酔いしれて。【脚本家・生方美久のぽかぽかひとりごと】
家族とか命とか季節とか

現在、脚本を担当したドラマ「海のはじまり」が放送中です。これを書いている今は、3話が完成した翌日。日々撮影や編集、打ち合わせなどが並行して進み、スタッフもキャストも忙しい毎日を過ごしています。が、わたしは一足お先にスケジュールに余裕が生まれました。実は初回放送の数日前に最終話の初稿が完成していまして、一日十数時間パソコンに向かう地獄の日々を脱却したのです! ドラマが終わっても登場人物たちはどこかに在り続けますが、ドラマとしての行きつく先はもう決まっています。最後まで夏くんや海ちゃんを見守っていただけたらうれしいです。あー、長かった。連ドラは長い。こんなに書いていた期間を長く感じるのに、放送が始まるとあっという間なんですよね。連ドラのそんなところもすきです。あぁ、長かった……。お疲れさまでした……。
と、想い出に浸りたいところですが、脱稿はしていないので「海のはじまり」と向き合う日々は続いております。山々に囲まれた海なし県で生まれ育ち、カナヅチでまったく泳げないこの脚本家……一生懸命に“海”と向き合っています。
というわけで、隙間時間でパソコンのデータ整理なんかをしてみた。家にデスクトップがあるわけでもなく、ノートパソコン一台を商売道具に戦っているので、こいつが機嫌を損ねたら何もできなくなる。だからそろそろ買い替えたい。データが突然吹っ飛ぶのも怖いので、ドンキで新調したUSBに片っ端からぶち込んだ。そんな過程で、懐かしいなぁ~と過去の作品を眺めていたら、脚本家の仕事として書いた原稿より、シナリオコンクールに応募した原稿のほうが圧倒的に多くて驚いた。自分の経歴の浅さを痛感したし、あの日々のお陰で夢が仕事になったと実感した。
脚本家になる方法はいろいろあって、わたしの場合はシナリオコンクールで入賞したのがきっかけだった。初めて賞をもらったのは2019年のこと。伊参スタジオ映画祭シナリオコンクールで奨励賞をいただいた。その脚本を久しぶりに読み返し、まず抱いた感想は「下手くそだなぁ……」。そして次に「変わらないなぁ……」だった。

タイトルは「5月と春の花」。主人公は三十代半ばの男。妻を亡くし、5歳の一人娘を育てている。良く晴れた5月のある日、妻と出会った小学校に娘を連れてやってくる。すでに廃校になり、誰もいない校舎や校庭を娘と歩きながら、当時の妻を回想し、娘からは“母”である妻の姿を教えてもらう。主人公の男にとって、亡くなった妻には小学校の同級生だった姿も、恋人だった姿も、妻だった姿もある。でも、娘が見ていた“母”の姿は、近くにいたのに案外知らない。いなくなった今になってから、父と娘がお互いに“妻”と“母”を教え合う。そんな物語だった。
賞をいただけたとはいえ、まだ脚本を書き始めて1~2年程度の頃で、あまりにも拙い出来だった。特に意識して変えた覚えはないが、細かい脚本の書き方が今とは違っていて、とても恥ずかしい仕上がりだった。のだけど、あまりにも内容が自分すぎて笑ってしまった。そもそも「海のはじまり」を企画したとき、この作品のことは全く頭になく、「父親が主人公の話を書くのは初めてだなぁ!」なんて思っていた。残念な記憶力よ。しかも(妻ではないが)娘の母親が亡くなっているところも同じ。記憶力よ。父と娘の会話もなかなか自分すぎる部分が多々あったので、一部抜粋して紹介させてください。あ、役名は“父”と“娘”に変えています。これもほんと記憶力よ……という感じで。娘の名前が、過去のドラマの主要人物に使った名前だった。すっかり忘れていた。ほんとにこの手の名前が自分はだいすきなんだと実感。恥ずかしすぎるので伏せます。
娘「いつから春か知ってる?」
父「うーん……3月? あーでも立春って2月か……」
娘「匂いでわかるんだって」
父「匂い?」
娘「春になると春の匂いするんだって。そしたら春なんだって」
父「ママが言ってたの?」
娘「言ってた」
父「(懐かしんで)言ってそう」
娘「夏はいつから夏か知ってる?」
父「夏の匂いでしょ」
娘「違うよ。扇風機出したらだって」
父「……ママらしい」
5年前にこんな会話を書いていたこと、すっかり忘れていた。なのに、絶対わたしが書いたセリフじゃん……と笑ってしまったし、記憶がないことが怖くもなった。季節の話なんて延々とやってられる。あとこれ。来年小学校に入学する娘が「この学校に通いたい」と言い出したくだり。廃校の意味を説明する父親。
娘「小学校って言ったじゃん」
父「小学校だけど、もう小学校やってないんだよ」
娘「……終わったの?」
父「そう。この小学校終わりなの」
娘「小学校って終わるの? ここにあるよ?」
父「うーん……小学校の、建物はあるけど……なんていうのかな、小学校として、働いてないの」
娘「じゃあ、通うから小学校働かせて」
父「いや、違う……そういうことじゃなくて……」
娘「なんで終わっちゃうの?」
父「(ふと真顔になって)……終わるんだよ。なんでも。始まったものは、終わるの」
これはちょっと変化を感じますね! 夏くんは「終わったわけじゃないよ」と言ってましたからね!……なんにせよ、始まりとか終わりとか、そういう話がすきなのも変わってないなと思いました。この後、数作コンクールで賞をいただいたり、デビューしたりしたんですけどね。変わらないもんですね。

データの整理を続けていたら、今度は映画学校に通っていたときの資料や原稿が出てきた。クリエイターコースというやつで、半年だけ映像制作の勉強をしていた。そこで約10分の短編映画をつくったのだが、その内容が「予期せぬ妊娠をした女性の葛藤」だった……。記憶力よ。こちらのことも、「海のはじまり」を企画したときは全く頭になかった。最終話まで書いた今になって「そういえばこんなのつくった~!!!」と記憶の波がバシャバシャ打ち寄せて溺れている。ただでさえカナヅチなので大変。誰か助けて。
根底にある“描きたいもの“は、脚本を書き始めたときから何も変わっていない。デビューのきっかけになったフジテレビヤングシナリオ大賞の「踊り場にて」や、デビュー作の「silent」が、家族がテーマの作品ではないので意識しなくなっていたが、シナリオコンクールに送っていた脚本はほとんどが「家族」「命」をテーマにしたものだった。それを描きたくて映画監督になろうと思っていた。連ドラ三作目の「海のはじまり」。実はこれが初めて自分からテーマを発案した作品だ。「silent」は「手話を使ったラブストーリー」「いちばんすきな花」は「男女の友情」をテーマにしてほしいとプロデューサーから依頼を受けて書いている。いざ、自分で描きたいものが描けるチャンスが来たとき、「家族」と「命」を提示するなんて、必然でしかなかった。
脚本に出る個性は、良く言えば「作家性」、悪く言えば「クセ」と言われる。褒めてくれる人は「作家性があって良いね」、貶してくれる人は「クセが強くて良くないね」という。似たような作風ばかりになるのは、今後の作家人生を考えると良いことには思えず、違ったテーマで、違った雰囲気で、違った個性を……と考えてしまいがちだ。でも、どんなに意識して変えようとしても、行きつく先は「家族」と「命」なんだと思う。記憶から消していた下手くそな過去作を読み返して、それがクセでいっか!と思えた。また5年後、脚本家を続けているかどうかもわからないけど、きっと「海のはじまり」のことを忘れて、家族がどうの、命がどうの、季節があれで、終わりと始まりが……と、しつこく描き続けていると思う。
生方美久(うぶかたみく)
1993年、群馬県出身。大学卒業後、医療機関で助産師、看護師として働きながら、2018年春ごろから独学で脚本を執筆。’23年10月期の連続ドラマ「いちばんすきな花」の全話脚本を担当。