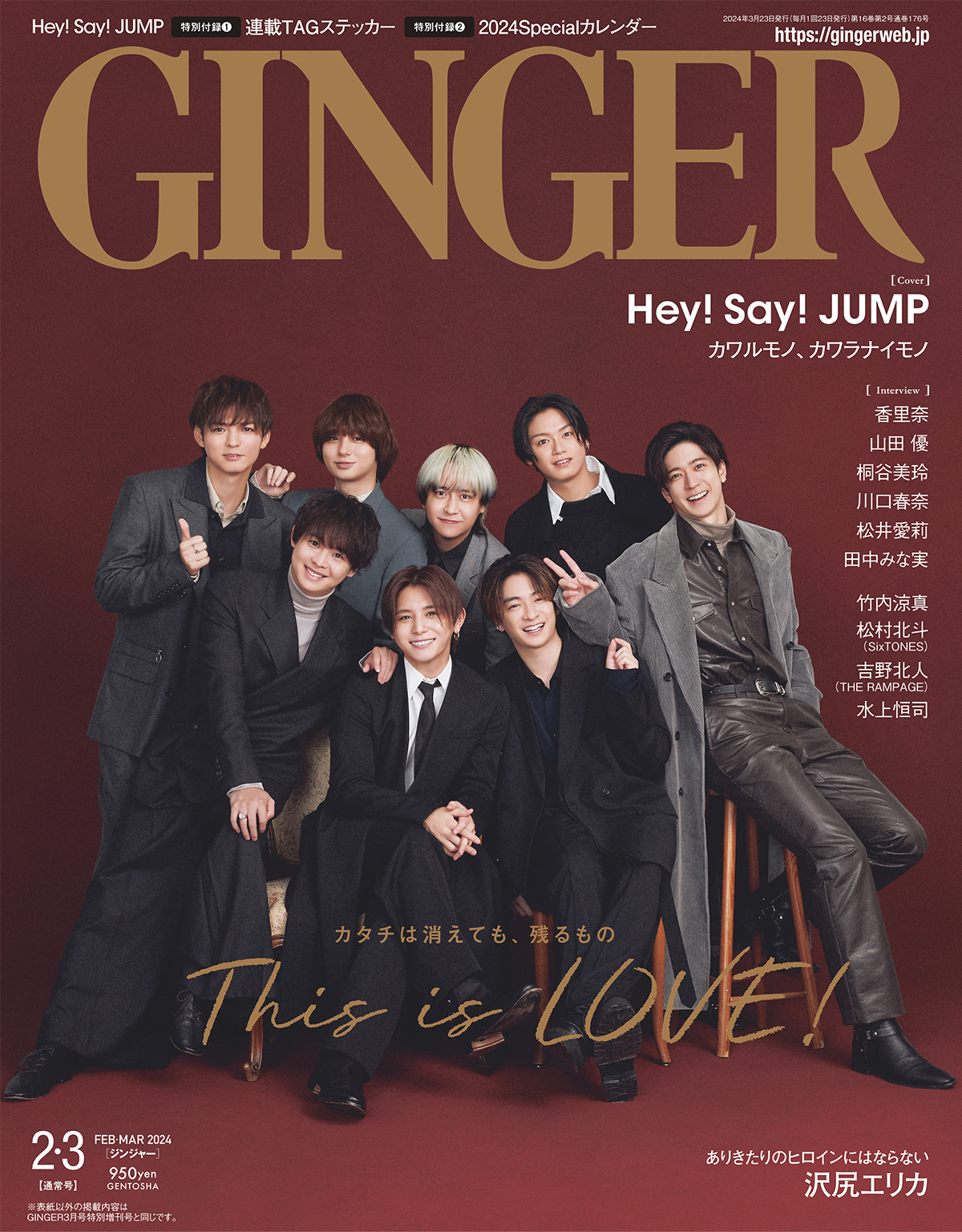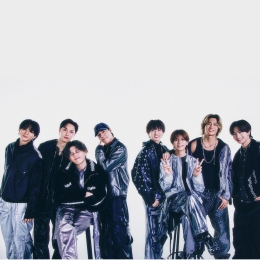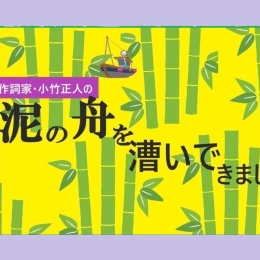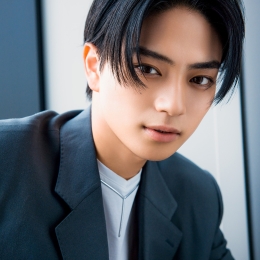“わたしの心地よさ”を基準に行動することが、ウェルビーイングに生きるカギになる。そのために、もっと自分自身を知る=自分のトリセツを手に入れませんか? 保健学博士の島田恭子さんがナビゲート。【連載「自分学 わたしのトリセツ」vol.30】
ココロとカラダを育む「ホルモン」の不思議な力〈前編〉

今月は私たちのカラダとココロの奥深くで、まるで魔法のように働いている「ホルモン」について、みていくことにします。
ホルモンは、私たちの「トリセツ」に深ーく関わっています。なぜなら、目には見えないのに、気持ち、エネルギー、健康、ビューティ…あらゆるところに影響を及ぼしているからです。それでは前編・後編2回合わせて、ホルモンを味方につけ、心地よく生きるヒントをお届けします。まとめて読んだら、知って得する情報が満載です!
ホルモンってどんな存在?体の奥で働く不思議なメッセンジャー

ホルモンは、体内で作られるごくごく微量の化学物質で、血液に乗って全身を巡り、細胞や器官に命令をする「メッセンジャー」のような役割を担っています。その数なんと100種類以上で、今もなお新しいホルモンが発見され続けているほど。私たちの体ってほんとうに神秘に満ちていますよね。
ホルモンは、体の状態を一定に保つ「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」に深く関わり、成長、代謝、生殖、感情など、あらゆる生命活動を調整してくれる「潤滑油」のような存在です。ほんの少しの量で劇的な効果を発揮するため、その「量」と「バランス」がとても大切。体の中でホルモンが必要な時期に必要な量だけ作られることで、体のバランスが保たれています。多すぎても少なすぎても、心身にさまざまな不調や病気を引き起こす可能性があります。
ホルモンは「適正な量」がとっても大事で、過剰でも不足でも問題なのは、ホルモンが単に「量」の問題ではなく、「バランス」が大事だからです。たとえば、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンのバランスが私たちの月経周期を調整しており、このバランスが乱れると生理不順につながることが知られています。また、ストレスを感じた際に分泌されるコルチゾールが過剰になると、他のホルモンの分泌が低下したり、肌トラブルや精神面への影響を引き起こす可能性もわかっています。このように、ホルモンは一つひとつが独立して働くのではなく、互いに影響し合い、体全体の調和を保っているんですね。
ホルモンの不思議

ホルモンは人間固有のものではなく、動物や植物にも存在し、生命活動を支えています。たとえば植物にも「植物ホルモン」がありますよね。植物自身が成長したり、環境に適応したりするために体内で作り出す化合物です。細胞の伸長を促進するものもあれば、休眠を促すものもあります。
また、猫や犬といった動物たちも、フェロモンという化学物質を通じて感情や行動に影響を受けています。猫が顔をこすりつけてくるのは、顔面のフェロモンを擦り付けて安心感を得るためだといわれています。不安を感じると肉球からフェロモンが出たり、尿マーキングをしたりすることもあります。
私たちの体はもう少し複雑で、それぞれ異なる重要な役割を持つホルモンが数多く存在します。たとえば、脳の奥にある脳下垂体はとっても小さい部位ですが、ここから多くのホルモンが分泌され、他の内分泌器官に指令を出しているんです。
ここでは特に私たちの心身の健康に深く関わるホルモンをいくつかご紹介しましょう。
成長ホルモン:脳下垂体から分泌され、骨や筋肉の成長・修復、肌の再生、疲労回復、脂肪燃焼促進など、まさに「若返りホルモン」とも呼ばれるいろんな働きをしますす。特に睡眠中に多く分泌されるため、質の良い睡眠が大事です。
甲状腺ホルモン:喉の下あたりにある甲状腺から分泌され、全身の代謝を活発にする働きがあります。このホルモンが過剰になると、食欲が増しても体重が減ったり、イライラしやすくなったりする「バセドウ病」の原因となることもあります。
副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど):腎臓の上にある副腎から分泌され、水分やミネラル、糖分の量を調節します。ストレスを感じた際に分泌が増えるため、「ストレスホルモン」とも呼ばれます。適量であれば体を防御する重要な役割を果たしますが、慢性的なストレスで過剰分泌が続くと、心身に疲弊をもたらし、不眠やうつ病、生活習慣病につながる可能性がでてきます。
インスリン・グルカゴン:すい臓から分泌され、血液中の糖分(血糖値)を調節します。インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血糖値を上げる働きがあり、このバランスが崩れると糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。
女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン):主に卵巣から分泌され、女性の体と心の健康に深く関わります。エストロゲンは肌の弾力や水分保持能力を高め、骨の健康を保ち、自律神経のバランスを整えるなど、女性らしさを育むホルモンです。プロゲステロンは妊娠の維持や基礎体温の上昇に関わります。これらは月経周期やライフステージによって分泌量が大きく変動し、心身に大きく影響を与えます。
アドレナリン・ノルアドレナリン:副腎髄質から分泌され、ストレスや興奮時に全身を臨戦態勢にする「闘争・逃走反応」に関わります。集中力や行動力を高める働きも持ちますが、過剰なストレス下では心身に負担をかけます。
知っておきたい女性ならではのホルモンの働き

ホルモンの全体像が見えてきたところで、お次は、私たち女性ならではのライフステージによるホルモンの働き、女性だからこそ知っておきたい、感情の変化やお肌、睡眠への影響についてみていきましょう。
女性ホルモンとライフステージ
女性の体は、ライフステージごとにホルモン分泌の量が大きく変わり、それが心身にいろんな影響を与えます。その変化は、まさに女性が自分らしく健やかに生きるための「トリセツ」を読み解くうえで知っておくべきことですね。
思春期:エストロゲンの分泌が増え始め、体が成熟する時期です。初めての月経を迎え、子宮や卵巣が発達していく過程で、月経不順や月経痛といったトラブルも現れやすいですが、これは体が変化している大切なサインでもあります。この時期は成長ホルモンの分泌も多く、身体を大きく発達させようとする段階です。
性成熟期:エストロゲンの分泌が最も盛んな時期。月経周期が安定し、心身ともに充実する一方で、子宮内膜症や子宮筋腫など、女性ホルモン量が多いことで発症・進行しやすい病気にも注意が必要です。月経周期はエストロゲンとプロゲステロンのバランスで調整されており、ストレスや疲れによって乱れやすいものです。日々の忙しさから不調のサインを見過ごしてしまうこともあるため、予防や早期のケアが大切ですね。
更年期:通常40代後半から50代にかけて、卵巣機能の低下によりエストロゲンの分泌が急激に減少する時期。このホルモン環境の大きな変化が、のぼせ、ほてり、イライラ、不眠、気分の落ち込みといった「更年期症状」を引き起こすことがあります。男性にもテストステロンの減少による更年期症状はありますが、女性ほど急激ではないため、症状も穏やかなことが多いとされています。
老年期:女性ホルモンの分泌がほとんどなくなる時期。エストロゲンの減少により骨密度が下がり、骨粗しょう症のリスクが高まります。これまでの生活習慣が心身の状態に影響を与える時期ともいえるでしょう。
ホルモンが感情や気分に与える影響

ホルモンは、私たちの感情や気分に深く関わっています。特に女性は、女性ホルモンの変動によって気分が左右されやすい傾向があります。
エストロゲンは、気分を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の働きに影響を与えます。エストロゲンが減少するとセロトニン伝達機能に障害が起きるため、気分が不安定になりますから、抑うつや不安感、イライラ、涙もろさなどを感じやすくなることがあるんです。これは月経前症候群(PMS)や更年期障害の精神症状の一因とも考えられています。女性ホルモンは、心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を促進する副交感神経の活動もサポートするため、その変動が自律神経のバランスに影響を与え、心身の不調を引き起こすことにもつながるんですね。
また、ストレスを感じると、コルチゾールやアドレナリンといった、いわゆる”ストレスホルモン”が分泌されます。これらは体を防御する役割を持ち、集中力や行動力を高める良い働きもありますが、慢性的なストレスによって過剰に分泌され続けると、不眠やうつなどの精神疾患につながる可能性もあります。このようなストレスによる自律神経の乱れは、頭痛、吐き気、便秘、肩こり、めまいなど、様々な身体の症状を引き起こすこともあります。
ストレスの多い現代社会。性別を問わずホルモンバランスの崩れが加速していそうです。とくに女性は、月経周期やライフステージによるホルモン変動に加え、社会生活でのストレスが重なることで、心身の不調を抱えやすい状況にあると考えられます。これは単に「年齢のせい」などでは片付けられない、もっと複雑な問題ですね。ストレス社会を生きる私たちにとって、ホルモンケアは年齢に関わらず、必須のセルフケアであると言えるでしょう。
ホルモンと身体の変化
ホルモンは、感情だけでなく、私たちの体の様々な機能にも影響を与えています。
睡眠:睡眠はホルモン分泌と密接に関わっています。特に成長ホルモンは深い睡眠中に多く分泌され、肌の再生や疲労回復を促します。睡眠を促すメラトニンは、成長ホルモンと並ぶアンチエイジングホルモンでもあります! 女性ホルモンのバランスの乱れは不眠を引き起こす原因にもなり、逆に睡眠不足は女性ホルモンの分泌に悪影響を与えます、悪循環ですね。睡眠は量よりも「質」が重要であり、深い睡眠をしっかり取ることがホルモンバランスを正常に保つ鍵となります。睡眠大事!ですね。
肌:エストロゲンは肌の弾力や水分保持能力を高め、肌を滑らかに保ちます。しかし、ホルモンバランスが乱れると、肌の乾燥やシワ、ニキビ、体毛の増加など、様々な肌トラブルにつながることがあります。ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌も、肌荒れの原因になります。
認知機能:女性のアルツハイマー病やその他の認知症発症率は男性の約2倍と言われており、性ホルモンとの関連が研究されています。また更年期障害の治療で行われるホルモン補充療法(HRT)やテストステロン値も高齢者の認知機能との関連が注目されています。一方、食べ物をよく噛むことで分泌される唾液に含まれるパロチンという成長ホルモンの一種は「若返りホルモン」とも呼ばれ、認知症の予防に効果があると言われています。
いやぁ、ホルモン、奥深いですね…。今回は、ホルモンの基本的な知識から、私たちのライフステージや感情、身体に与える影響についてみていきました。ホルモンってこんなにも私たちの心身の健康に深く関わっているのですね。
次回は、私たちのココロを満たす「幸せホルモン」の秘密に迫り、すぐに実践できるホルモンにまつわるセルフケアの方法を、さらに詳しくご紹介していきます。どうぞお楽しみに!
参考文献
田中越郎 (2021)イラストでまなぶ生理学 第4版 医学書院
島田恭子(しまだきょうこ)
予防医学者・保健学博士。医学や心理学の知見を、女性のウェルビーイングに役立てたいと活動中。(社)ココロバランス研究所代表。
https://customer-harassment.org/kyokoshimada/