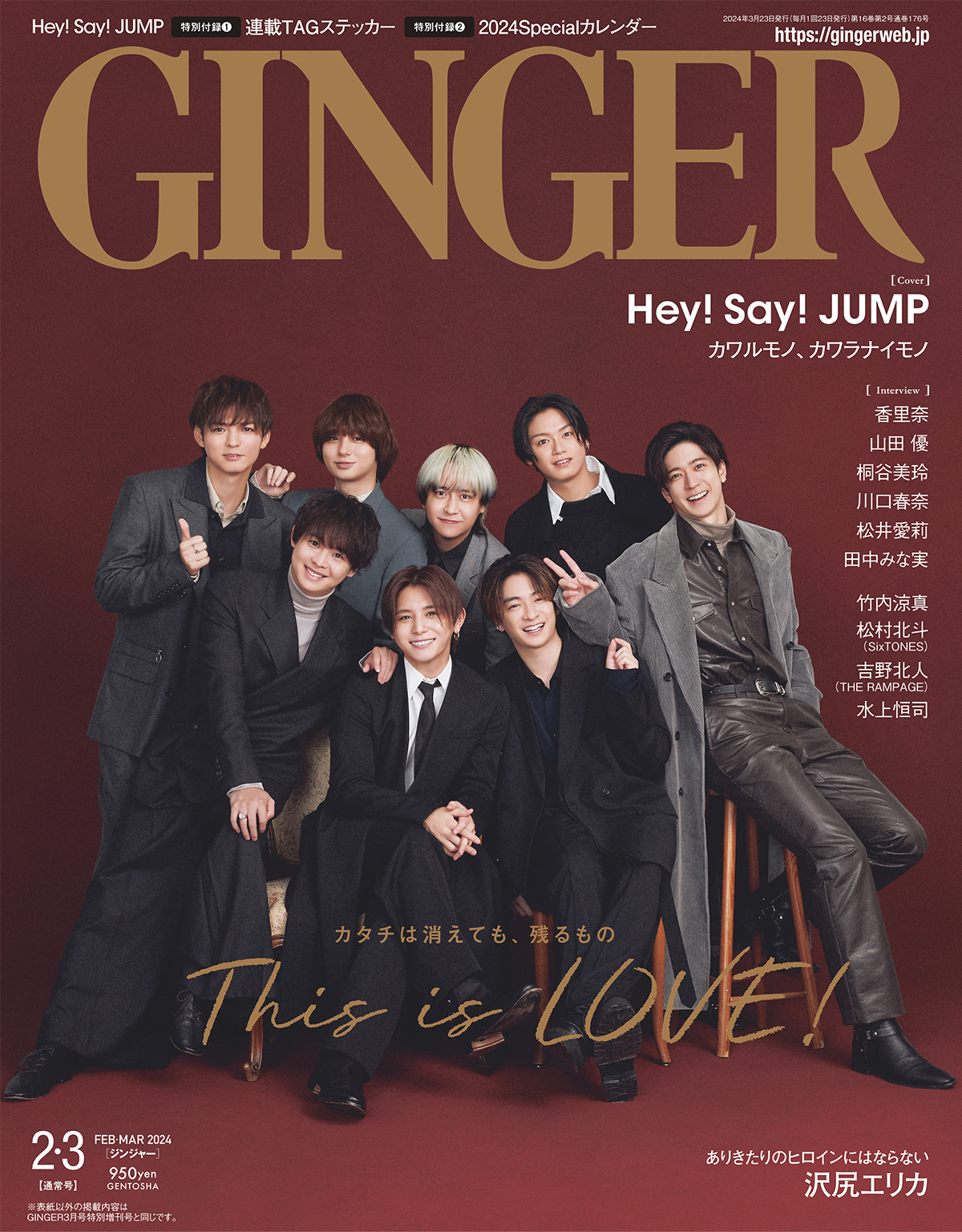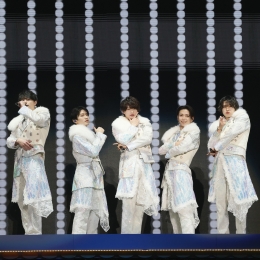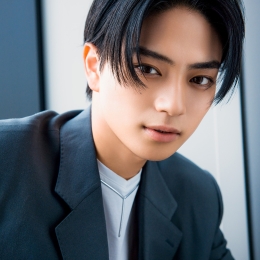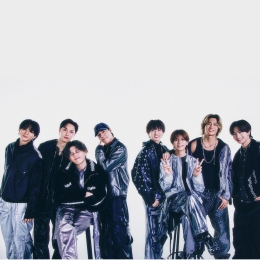自分に似合う服を選ぶとき、着こなしを考えるとき、知っておきたいファッション用語やテクニック、今どきの常識を、スタイリスト青木貴子さんが独自の視点を交えながら解説する連載「大人のおしゃれワード集」。

PHOTO=wd_emtm24
前回は、着物ライフの気軽な始め方についてお話ししました。お正月はお着物に挑戦できましたでしょうか? 2月の節分(2021年は2月2日)までは初詣期間としている社寺が多いので、まだまだお着物を着て初詣なんてことも可能です。まとうだけで晴れやかな気持ちにしてくれるお着物の力を借りれば、ご利益もアップしそうです。
今回はさらに豆知識、お着物の種類や格をテーマにお届けします。
着られる着物、着られない着物

(c)goo922/Shutterstock.com
着物には厳格に格やルールというものが存在します。洋服でもTPO(時と場所とシーン)によってドレスコードがありますが、着物の場合は、TPOに立場(というのかな、ちょっと説明が難しいけれど)がプラスされます。たとえば未婚か既婚か、あるいはホストかゲストか、その人の立場によって、ふさわしい着物が変わってくるのです。
成人式で着た「振袖」は、未婚女性が着るもの(最近はより自由に、既婚でも着る人が増えているようですが)。また、格が高いとされる「黒留袖」は既婚女性が着るもので、自身の子供の結婚式、または仲人を務めるときくらいしか着られません(これは相当、着る機会が限られますよね〜!)。と、いろいろな決まりごとがあるのです。
知っておきたい着物の格
まずは着物の格を知っておくと、自分に必要な着物がどれか見えてきます。
着物は「礼装」「準礼装」「略礼装」「おしゃれ着」「カジュアル普段着」に分かれています。
未婚者にとって、すべての着物のなかで一番格上な礼装は「打掛」。

PHOTO=与儀美容室
これは自身の結婚式のときにしか着られない、超限定アイテム! そう思ったら結婚式のときにぜひとも袖を通しておきたいところ。ウエディングドレスと打掛、できたら両方楽しみたいですよね〜。
そして既婚女性にとっての最高峰の礼装が「黒留袖」。

PHOTO=nonmama0312
この着物の特徴は、
・染め抜き五つ紋(家紋が5箇所に入っている)
・色は黒
・裾まわりのみに絵羽付け模様(縫い目をわたって一枚の絵のように模様が入っているもの)
の3つ。黒留袖は素敵ですが、前述のように出番がかなり限られているお着物。ある意味相当贅沢ですよね。
次に格が高いのが「色留袖」。

PHOTO=ささや呉服商
こちらは既婚でも未婚でも着られ、
・紋付き(五つ紋、三つ紋、一つ紋いずれでも可)
・色は黒以外
・裾まわりのみに絵羽付け模様
が特徴として挙げられます。五つ紋にすれば黒留袖と同格の礼装になります。とはいえ、結婚式において母親は黒留袖を着るのがしきたりなので、親戚の結婚式や、授章式なんかに着る感じ。
三つ紋、一つ紋と紋の数が少なくなるほど気軽に着られるものになりますが、これらは準礼装とされ、もちろん結婚式も祝賀会などのパーティーもOK。
淡く綺麗な明るい色味のものが多いですが、写真のようにシックなタイプも素敵です。
色留袖と同格なのが「本振袖」。

PHOTO=415youko
こちらは基本、未婚者の第1礼装で、着て行ける場所は成人式、自身の結婚式、友人の披露宴、お初釜などのお茶会など。既婚でも着用可という感じに変わってきているようですが、トウが立ってくるとなかなか着づらい。でも、中振袖(本振袖より袖が短いもの)なら、年を重ねても大手を振って着られます! かくいう私も、成人式に着た振袖はお仕立て直しをして、中振りにして今でも着ています。中振りに仕立て直すの、オススメ!
そして「訪問着」。

PHOTO=ささや呉服商
訪問着の特徴は
・全身に華やかな絵羽付け模様
という点にあります。胸や袖にも柄があるから色留袖よりも華やか。紋なしだと略礼装ですが、一つ紋をつければ準礼装として通用します。招待された結婚式や披露宴、さまざまなパーティー、子供の行事(お宮参り、七五三、入卒式etc)などなど。一枚持っているといざというときにちゃんとした人に見せてくれる強い味方(笑)。
訪問着と似ているのが「付け下げ」。

PHOTO=sarajin0817
・反物のまま染められている(=絵羽付けでない)
・訪問着より模様の少ない、控えめな柄
というのが特徴です。反物で染められていて柄が分散するので、絵羽付け模様の訪問着よりは控えめで落ち着いた印象になっています。でもその分、華やかな帯を合わせることで変化をつけやすいというメリットが! 紋を付け、格のある帯を合わせれば準礼装に見なされ、結婚式や改まった席へも着て行くことができます。
そしてお次は「色無地」。

PHOTO=tastas93
・読んで字のごとく、黒以外の無地
・地紋があるものとないものがある
という特徴があります。地紋とは、染める前の生地の段階で織り出されれている模様のことであり、先ほど語った「紋」とは違います。

PHOTO=ささや呉服商
色無地の中でも地紋があるものは、紋を入れたら準礼装として着られます。実は、一つ紋を入れた地紋のある色無地が一番便利かつ重宝する着物ではないかと思います。これは訪問着や付け下げと同じ格付け、つまりちゃんとした場面でも着られ、合わせる帯や小物によっては街着にもなります。着物自体に華やかな柄がない分、どんな柄の帯でもコーディネート可能、つまり着回しが効きます。
そして続くのが「紋付きの江戸小紋」。
まず江戸小紋とは、このあと出てくる小紋(パターン柄に染められた着物)の一種ですが、染め方がほかの小紋とは少々異なり、白生地に細かい柄が一色のみで染め上げられています。

PHOTO=suzuki.yumiko
その江戸小紋の中でも、裃(かみしも)小紋と呼ばれ格の高い鮫、行儀、各通し(それぞれ柄の呼び名)小紋に一つ紋を入れると、一つ紋の色無地同様に略礼装として着ることができるのです。

鮫小紋
江戸小紋は粋な感じがして個人的には好きな着物のひとつ。
礼装ではない、おしゃれ着に当たるのが「小紋」「御召」「紬」。
ここで知っておくとわかりやすいのが“染め”か“織り”かという違い。着物は一般的に染め(白い生地を染めて色を付ける)のほうが、織り(糸の段階で染められたものを生地に織る)よりも格上とされます。ちなみにこれが帯になると、逆に織りのほうが格上です。
「小紋」は染めの着物で、柄や染め方次第でよそ行き着にもカジュアル着にも振り分けられます。御召と紬は織りの着物。紬には「大島紬」や「結城紬」などいくつか代表的なものがあります。

PHOTO=ささや呉服商
絹独特の光沢感が素敵です。ちょっとしたお食事会や観劇、パーティーなどに向いています。
そしてカジュアル着に当たるのが「絣」「銘仙」「ウール」「綿」「浴衣」など。`
着物をこれから気軽に、おしゃれに着こなしたいという人は紬を、もっとカジュアルに楽しみたいなら銘仙や夏の浴衣から始めてみるといいかもしれません。
マッチングに注意!着物と帯の相関関係
そしてどの着物を着る時も、その格に合わせた格の帯を合わせる! これが最重要ポイントです。黒留袖には「丸帯」「袋帯」、色留袖、振袖には「袋帯」、訪問着、付け下げ、色無地には「袋帯」「織りの名古屋帯」、小紋、御召には「袋帯」「織りの名古屋帯」「染めの名古屋帯」、紬には「織りの名古屋帯」「染めの名古屋帯」と、それぞれふさわしいマッチングがあります(細分化するともっと種類はさまざま!)。
見る人が見ると格合わせの正否がわかってしまうので、着慣れるまではその道に詳しい人にチェックしてもらうのがベスト。何でもそうですが最初はみんな初心者。恥ずかしがらず面倒がらず、教えてもらうのが早道です。
今回の記事を読んだだけでは理解しきれなくてももちろん大丈夫。興味が湧いたら、さらにネットや本で調べてみてください。へーこれがそうなんだ、こんなものなのか、と目にしていくと、ますます面白くなると思います。
あー、今回もお手入れの話までいけなかった・・・着物、語るところ多いなぁ〜! それだけ着物は奥が深い世界、洋服とはまた違った魅力に溢れています。せっかくお着物の国にいるのですから、ぜひともワードローブに加えて、素敵に着こなしてください!