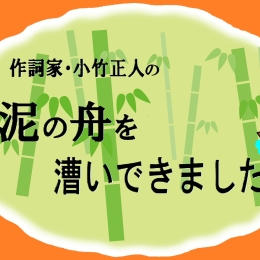本好きライター 温水ゆかりさんがおすすめの1冊を紹介する連載「週末読書のすすめ」。紙に触れてよろこぶ指先、活字を目で追う楽しさ、心と脳をつかって味わう本の世界へ、今週末は旅してみませんか。
『つみびと』山田詠美 著

見えない沼底に棲む、暗くて重い罪たちよ
ガール・ミーツ・ボーイ。
恋に落ちる瞬間が、こんな風に描かれた小説を読むのは初めてかも。
高校を卒業してファミレスで働き始めた笹谷蓮音は、そこで松山音吉というアルバイトの大学生と出会う。
「音つながりですよっ!」
おどけて音吉を笑わせる。こうして笹谷蓮音は「殺人者の第一歩を踏み出した」。
とはいえ、急いで書くと、これは殺人そのものをクローズアップするお話ではない。なぜ彼女は殺人者になってしまったのかと、原因を追求したり明らかにしたりするお話でもない。
『つみびと』を英語で表記した部分に、意図というか哀しみというか祈りというか、著者がいまの日本社会をどう捉えているかが、鏡のように写しだされている。
「SINNERS」。そう、複数形なのだ。

Licensed by Getty Images
題材は、誰もが衝撃を受けたいたましい事件だ(2010年)。
風俗で働く若いシングルマザーが、幼児2人をマンションの一室に閉じ込め、ときどき帰宅してコンビニで買ったお握りやお菓子を与えていたものの、結局は餓死させてしまう。
インターフォンから漏れてくる子供たちのかすかな声に気づき、通報したマンションの住民もいたが、公的機関が機能しなかったことでも批難の声が高まった。
彼女の実父は、高校スポーツ界では伝説的な指導者。そんな熱血教師の娘がこんな事件を起こすなんて、という(私に言わせれば親のスキャンダル扱いにする筋の悪い)報道もあった。
お話は3パートに分かれる。
笹谷蓮音の〈娘・蓮音〉と題したパート、蓮音の実母の〈母・琴音〉と題したパート、蓮音の子供達である4歳の男の子と3歳の女の子の〈小さき者たち〉のパート。
各章は3パートから成り、レゴブロックを積み重ねるようにして、計9章+エピローグの物語が進んでいく。
3パートの文体は違っている。文体ってなんだろう? 登場人物の声をもっともよく響かせるための最適の容れ物と考える私は、うんうん、この文体の違いが、この小説は効いてるのよね、と、ひとり深くうなずく。
何が効いてるって、それぞれの容れ物の中で起きていることの時制が違うから、3パートをあわせると、この小説にはものすごく長い時間が流れているのだ。琴音のパートに登場する母(蓮音にとっては祖母)まで含めると、なんと4世代。
小説は〈母・琴音〉のパートの、こんな書きだしから始まる。
「私の娘は、その頃、日本じゅうの人々から鬼と呼ばれていた。鬼母、と」
琴音は娘が子供を死なせてしまったのは、蓮音が小さい頃、育児を放棄して逃げ出した自分にも非があるのではないかと思い悩む。そして自分が何を考え、どう行動してきたのかを自分史として語り始める。
実父の暴力の餌食になっていた少女時代。そんな父に従順だった母。
父亡き後(実はここにも仕掛けがあるけれど、それは読んで確かめて)、家に入りこんできた養父から性的虐待を受けていたこと。
年上の熱血指導者に出会って結婚するまで、リストカットを繰り返していたこと。
一方、女子刑務所に入った〈娘・蓮音〉のそれまでを描くパートはこう(文体は起こっていることを広角で捉えるのにたけた三人称)。
母の琴音がいなくなった家で、長女の自分が弟や妹の面倒をみなければならず、孤立したアダルトチルドレンだったこと。
中高時代は、やりたい盛りの同級生や遊び仲間の間で“都合のいい女”として回され、彼女自身もまた自分を粗末に扱っていたこと。
育ちのいい温厚な音吉とでき婚をし、幸福な新婚時代を送ったこと。
でも古い毛布のように肌に馴染んだ不良仲間とのやりとりが恋しくなり、また彼らとこっそり遊ぶようになったこと。
この両者の間にあって、唯一進行形の出来事を受け持つのは〈小さき者たち〉のパートである。
このパートでは、睦み合う母と子の姿を俯瞰で描写したり(ギャル語を消音にすれば「聖母子像」のようでもある)、子供の肩口に下りていって、4歳の男の子の視点で母の姿を仰ぎ見たりする。
視点の高低差、自由自在。「です・ます」の優しい口調が、児童文学の世界を思わせる。
でもここは、悲劇に向かうカウントダウンのパートでもある。
母親の姿が見えなくて、お腹が空いて、喉も渇いて、妹はグッタリなっていて。
子供たちの不憫さに、思わず落涙してしまう人もいそうだ。
なにか犯罪が起こったとき、因果律で考えたくなるのは世の常。“親の因果が子に報い”みたいな訳知り顔の成句もある。
2010年、現実のこの事件が発覚し、ワイドショー的報道が繰り返されたとき、“やっぱり子を捨てた母親の子は、自分の子を放置して、殺すような親になっちゃうのね”という因果律で納得し、私には関係ない事件として、忘却箱に収納した人もいると思う。
誤解を怖れずに書けば、この小説はそういった風潮に異をとなえるために書かれた。
子供たちの受難は、女たちの受難でもある、と。
誰かの不幸ではなく、女の誰でもそうなる可能性のある不幸社会だ、と。
家庭内暴力、性的虐待、ネグレクト(育児放棄)、性的搾取、無知、無関心、無理解、無慈悲、不寛容。
著者は、これらの社会学的な用語をいっさい使わず、そういった状況下にある者の心、あるいは虐げられているという知覚すら持てない心を、一つひとつ腑分けするように書いた。これは小説にしかできないこと。そういうチャレンジングな作なのだと思う。
もう何十年も前になるが、ある女性作家が養父に性的虐待を受けていたことを小説にした。その女性作家は、ある文芸評論家に「親の悪口を書くもんじゃない」とさとされたという。
唖然とした、ムカついた、誰だか知らない相手なのに、憎しみまで感じた。
正論だと思って正論をはく人の正論は、百億光年譲って正論だとしても、全然正義じゃない。正論は現実を固定させるだけだ。
そんなことを思った場面がある。
蓮音が正論をはく大人たちに囲まれ(音吉の両親、蓮音の父親、そして音吉)、流れで離婚に追い込まれるシーンだ。
母親としてちゃんとしろ、朝帰りはするな、悪い仲間と付き合うな。すべてもっとも。もっともだけれど、そのバーをクリアしろと突き付ける態度には、上から目線の無慈悲さがある。正論しか受け付けない不寛容さが。
2人の子供を連れて離婚した蓮音に、手を差しのべる者はいなかった。孤立した母親はさすらう。
著者は蓮音の内面をこう書く。
「蓮音は、いつも自分の身に降り掛かる災難を、どうにかしてやり過ごそうとして来た」「頭の中に歌を流すこともある。目を閉じて何も見ないようにすることもある。ただ記憶を想像のペンキで塗りつぶしてしまうことも。でも一番効くのは、自分の魂をどこかに飛ばしてしまうことだ。そうすれば、残るのは、空っぽの体だけ。脱け殻になってしまえば大丈夫。だって、脱皮の後に置き去りにされた蛇の脱け殻が、怒りのとぐろを巻いていたなんてこと、ある?」
怒りや痛みがマックスになると、魂を飛ばしてやり過ごす。魂は飛んでいった先で、休息できているのだろうか。いや、できていないと思う。
そしてそんな魂に無関心な私たちもまた、『つみびと』なのではないだろうか。
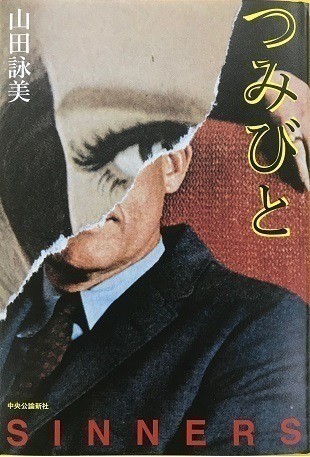
『つみびと』
山田詠美 著/中央公論新社
「私なりの『罪と罰』を描きたかった、と言ったら、あまりにも大それているでしょうか」(版元の つみびと 特設ページより) ――とは山田詠美氏の言葉。ひとつの痛ましい事件に端を発し、いくつもの角度から無自覚の罪や無意識の罪をもあぶりだす長編小説。日本経済新聞に連載され話題となった新聞小説。装画・装幀は横尾忠則氏。