本好きライター 温水ゆかりさんがおすすめの1冊を紹介する連載「週末読書のすすめ」。紙に触れてよろこぶ指先、活字を目で追う楽しさ、心と脳をつかって味わう本の世界へ、今週末は旅してみませんか。
『あちらにいる鬼』井上荒野 著
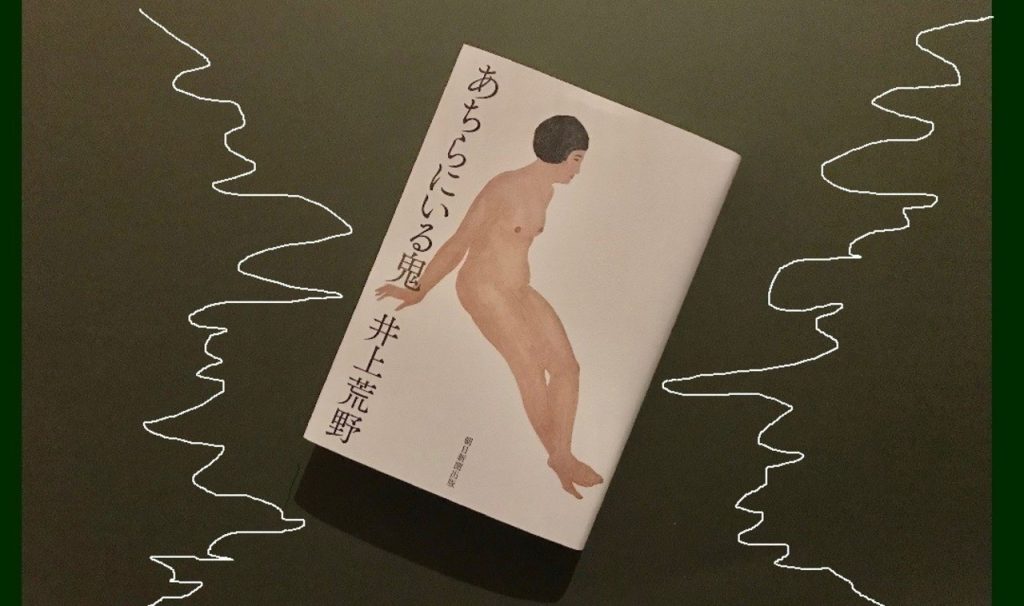
飼い馴らす鬼、解き放つ鬼。あなたの鬼はどんな鬼?
もうずいぶん昔のこと。取材で寂庵をお訪ねした折、壁に飾られていたものの話から、ふと寂聴さんが井上光晴さんとの関係を漏らされた。文壇事情に疎かった女性編集者と私は思わぬ告白に仰天。
帰り道、「そうだったの!?」「だったみたいね・・・」と、声をひそめて驚きを伝え合った。そういうとき、なんで小声になるんだろう。玄関での世間話から思わぬ話が飛び出し、偶然知っちゃって申し訳ないです、みたいな気持ちになっていたんだと思う。
とはいえ、お二人の関係がどうだったかを事細かに知っていたわけではない。いや、知っていたのに知らないと思っていた。そう、実は知ってたんです。今回は2冊目でそんな迂闊な話も。
まず、寂聴さん(当時は瀬戸内晴美)と井上光晴さんの関係が、最近『あちらにいる鬼』という小説になった。『あちらにいる鬼』のようなタイプの小説は、モデル小説と呼ばれる。モデル小説というのは、実在の事件や人物を当てはめて読むと、いっそう興趣が増すというもの。でも書き手の側から言えば、小説としての完成度を目指したものだから、あくまでフィクションとして読んで欲しい、ということになる。
古くは三島由紀夫に、『宴のあと』というモデル小説があった。都知事選に材を取り、料亭だの立候補だの着物だの宝石だの金一封だのと、端正な文章の中に世俗臭ムンムンの小道具がちりばめられているのが面白かった。プライバシー侵害で裁判沙汰になったことでも有名だ。
しかし、この『あちらにいる鬼』が裁判沙汰になる心配は一切ない。なんたって、著者の井上荒野さんは井上光晴さんの娘。西洋の慣用句を借りれば、「クローゼットの中の骸骨」(どんな家にもおおっぴらにできない隠しごとがある、の意)を取り出し、陽に晒すことにしたのが家族の一員なのだから。
井上荒野さんは、何度も寂聴さんに取材した(らしい)。そして寂聴さん自身が帯に「モデルに書かれた私が読み傑作だと、感動した名作!!」という大絶賛の言葉を寄せているのだ。こんなに祝福されたモデル小説というのも珍しい。
登場人物とモデルの関係を明らかにしておこう。
作家の長内みはるは、瀬戸内寂聴さん、同じく作家の白木篤郎は井上光晴さん(1992年逝去)、白木の妻・笙子は実際の井上夫人(2014年逝去)。幼稚園に通う白木夫妻の娘・海里が当時5歳の井上荒野さんだ。
物語は、みはると笙子の交互の視点で進む。
みはるが東京に借りた部屋で迎える「愛人の白木」、笙子が食事の支度をし、ノートに書かれた糸くずのような字を判読して原稿用紙に移し、時には編集者に内緒で代作もしている「夫の篤郎」。
不思議なことに、白木篤郎はどちらにいてもあまり変わらない。女性関係になると、自分に都合のいい嘘でみはるのことも笙子のことも丸め込もうとするが(二人とも信じていない、というか追求する気がない)、小説に対しては超誠実。
みはるには、原稿を書き上げたら編集者に渡す前に俺に見せろと言い、真剣に目を通し、アカを入れる。みはるは白木によって、自分の文章や小説を磨いていく。一方妻の笙子には、自分の名前で書くことを薦め、編集者にもそれとなく妻の文学的才能を喧伝する。
ここから先は余談になるけれど、井上光晴は「嘘つきみっちゃん」と呼ばれていた。(本書では「嘘吐きあっちゃん」)。久留米市生まれなのに満州生まれと言い、恵まれた家に生まれたのに貧しかったと偽り、学校にも行けなかったと学歴を低くし、初恋の少女は朝鮮人で女郎部屋に身売りされたと(ご本人に迷惑をかけるくらい)粉飾した。
マイナスカードをずらっと揃える。「事実より強度のある嘘をつけ」。これが井上光晴の“文学観”だった。そんな人だったから、たぶん喜々として、娘にも「荒野」という名をつけたのだろう。私はフェミナ賞受賞者として井上荒野の名を知ったとき、まさか本名だとは思わなかった。ずいぶん覚悟のあるペンネームだなあと思った。
『あちらにいる鬼』に話を戻すと、物語は、みはると白木の情事が始まった1966年に始まり、途中で「みはる」の章題が「寂光」に変わり、白木の闘病生活と最期を経て、2014年、笙子の命のロウソクがまさに消えようとしているシーンで幕を閉じる。
女達は対立しない。笙子は小説誌に掲載されたみはるの小説を読まないことでやり過ごし(読めば夫の影を感じるだろうから)、みはるは出口のない情事に出家という形で決着をつける。家庭を持った男と、恋多き女と呼ばれた女性作家の情事小説は、いつしかひそやかな絆で結ばれた女の友情小説に姿を変えていた。
あちらにいる“鬼”とは、右岸と左岸に立つ女同士が相手を指して言っているのではなく、二人でクスクス笑いながら、自分たちを翻弄した空の上の「嘘つきみっちゃん」を指している題名のように思う。ま、解釈は自由ってことで。
半世紀にも及んだ男女の旅路。井上荒野さんはこれを書くことで、真の意味で両親を成仏させたのだなあと思う。荒野ではなく、沃野の娘である。難しい言葉を使わず、平易な言葉で状況や心理を的確に表現する文章のムダのなさにもうなった。柔らかくて美しい小説だ。
そしてこの後、私はむしょうに瀬戸内寂聴の『場所』が読みたくなる。理由は分からない。寂聴さんつながりと言ってもいい。でも、だったら寂聴さんの別の小説でもよかったはず。
『場所』は77歳の寂聴さんが、多々羅川(徳島)、名古屋駅、京都の油小路三条、三鷹下連雀、西荻窪、など、戦火に焼かれた故郷、夫に別れを告げた場所、上京して男と暮らした場所などゆかりの土地に、我が半生を語らせるという自伝的回想小説だ。この本もまた、ムダのない文章とはどういうものかということを教えてくれる本で、“文章の魅力”つながりで再読の衝動にかられたのかなと思ったのだけれど・・・。

Licensed by Getty Images
本書で白木とみはるがタクシーの中から見る徳島の吉野川。吉野川は瀬戸内寂聴 著『場所』にも登場する。
14ヵ所目、最終篇の「本郷壱岐(ほんごういき)坂」を読んで、わ、と飛び上がる。ここに出てくる男って、これ、井上光晴さんではないですか! 知らなかった、いや、気づいていなかった。
男はこんな風に描写される。「新しい情事の相手は、これまでのどの男よりも強引でしたたかであった。妻子を溺愛しながら、常に複数の情事を重ねていた」。まさに『あちらにいる鬼』の白木篤郎そのもの。迂闊だった。気がついていれば冒頭の、寂聴さんがぽろっと井上光晴さんとの関係を漏らされたとき、どぎまぎしないで、「『場所』にも書かれてていましたものね」くらいの、はしっこい会話ができたのに。
作家の「私」と男は、壱岐坂に建った真新しいマンション「本郷ハウス」で、倦んだ言葉を投げ合う。この部屋に来ると早々と酔いに溺れ込む男は言う。
「もっと面白い話はないの」。「私」はやり返す。「酒の肴にするような話、してやるものか」。すると男は挑発する。「へん、それでも物書きか、どうしてそう、ほんとうのことしか喋れないんだろう。もっとホントらしいウソがつけないものかなあ」。そして男はちょっと威張る。「おれはね、天性の嘘つきなんだよ」「だから小説家の資格があるんだ」
こんな言葉のボクシング(=愛撫)をしながらも、「私」は男から離れられない。「私」が隠し持った虚無と、男に巣喰った孤独の形がよく似ているからだ。
出家したいと思うようになった衝動を、「私」は自分をパラフレーズしてこんな風に書く。「住いに馴れ、便利さに馴れ、愛に馴れ、生活に微温的な階調がかなでられてくると」「居ても立ってもいられな」くなる。「ひりひりした焦燥感に心を灼かれ」、「性懲りもない破壊願望に衝き動かされてしまう」と。
男が井上光晴さんだったと知って、あらためてぐっときたのはこのシーン。
「私が出家すると話した時、男は愕きもしなければ、止めようともしなかった」「ほうら、ホッとしている。しめたって」「当り」。「どちらからともなくコップを合わせていた。男の目の中から一挙に酔いが引いているのから、私は何故か傷ましい感情で、あわてて目を反らせていた」。
嘘つきみっちゃんにも唯一、無頼の衣装を着せられない箇所があった。目だった。
この短篇で死の床にある男と「私」が交わす会話は、本音を入れた袋の裏表をひっくり返してみたり、また元の閉じた袋にしてみたりの虚実の応酬。ああ、『場所』って何回読んでも大人の小説だなあ。
でも“2冊併せ読みを”とは言わない。それぞれ独立した作品だから。いま現れた傑作と、時に濾過された名品では、味わいが違うものだから。
香り華やぐ辛口の白ワインを楽しんだ数日後、今日はフルボディの赤ワインでも飲もうかな。そんな感じでどうぞ。
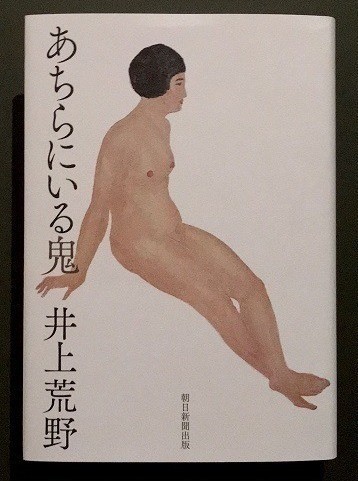
『あちらにいる鬼』
井上荒野 著/朝日新聞出版
小説家の父 井上光晴、母、そして瀬戸内寂聴をモデルに、作家生活30周年を迎えた井上荒野が書き上げた話題作。三人の稀有な関係が、井上の長女である著者しか持ち得ない視点で描かれている。帯には「モデルに書かれた私が読み傑作だと、感動した名作!!(瀬戸内寂聴)」と賛辞を掲載。











