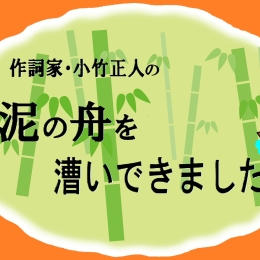本好きライター 温水ゆかりさんがおすすめの1冊を紹介する連載「週末読書のすすめ」。紙に触れてよろこぶ指先、活字を目で追う楽しさ、心と脳をつかって味わう本の世界へ、今週末は旅してみませんか。
『悪意』ホーカン・ネッセル 著
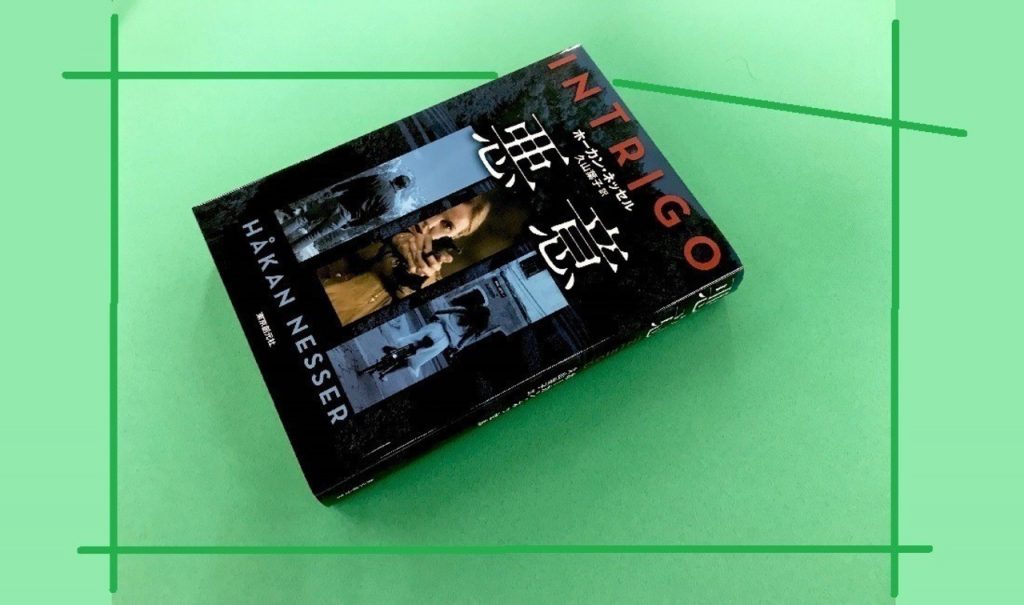
ふたつの眼を使って読み進めた“奥深”ミステリー本
それ自体で発光しているような底光りするタイトル。腹黒族としては手をのばさずにいられない。
5編の中短篇が収められている。
いきなり死人が蘇る「トム」、“作家とはねじくれた精神の者がなる職業です”と言わんばかりの粘着度にしてやられる「レイン ある作家の死」、昔の親友同士が大人になって再会する「親愛なるアグネスへ」、ハイスクール卒業後、一度も故郷に足を向けなかった男が帰郷して大事な告白をする「サマリアのタンポポ」、教師になろうとしている若者の心変わりを描く「その件についてのすべての情報」。
ミステリーに長年親しんでいると、ある種の「型」のメニューが頭の中にできる。ストーリーを追いながら、過去の類作を検索し、先の展開を予測するという実に不毛なことをしている。カッコつけて言えば、虫の目でストーリーを味わい、鳥の目で作品の位置付けをしているわけだが、そんなものなどぶっ飛ばすのが作家の腕の見せどころ。ホーカン・ネッセルは、スウェーデン・ミステリー界の重鎮だけあって、さすが。さまざまな趣向を凝らしている。

Licensed by Getty Images
順に見ていこう。
「トム」で蘇る死人とは、主人公ユーディットの義理の息子のことだ。トムは11歳年上の夫の連れ子で、17歳のとき失踪した。それから22年、真夜中にかかってきた電話の向こうからトムが現れる。ニヤつく声で、久しぶりだね、と。失神寸前のユーディットに、読者はすぐ気づくはず。トムの失踪には、なにか重大な秘密が隠されていると。
トムは小さい頃から感情を制御できない問題児だった。思春期には薬物中毒になり、腕に鉤十字の刺青を入れているような友人達とつるんでいた。その行状や義理の息子という関係からも、あること(=「型」)が推測できる。そしてそれは当たっていたのだけれど、この話には進んでも進んでもなお地雷が埋まってるかのような危うさがあって、第2や第3の爆弾が破裂する。夫の告白や夫の決死の行動などは、まったくの想定外だった。
重厚な伝記作家として知られるユーディットがようやく静かな生活を取り戻したとき、またもやループのような悪夢が電話口の向こうからやってくるというオチは、ほとんどホラー映画だろう。
「レイン ある作家の死」は、翻訳家の「わたし」が主人公。自殺した作家が奇妙な遺言を遺す。自分の最期の作品は翻訳でしか出版を許さない、と。そこで出版社が白羽の矢を立てたのが、かつて彼の作品の翻訳を手がけたことのある「わたし」。「わたし」は、ある街にアパートを借りて翻訳に専念する。なぜその街なのか。ラジオコンサートの中継で、妻の咳の音を聞いたからだった。彼女はあの街に住んでいるに違いない。
なんて奇妙な設定だろう。作家が外国語での出版を希望している意図も不可解なら、3年前に愛人のもとに走った妻の居所を突きとめようとする「わたし」の行動も不可解。未練とか、妻を奪還したいというのでもなさそうなので、不可解さは倍増する。
私はこう思いながら読んでいた。この男はきっと妻を殺したに違いない。なのに、ライブ放送で妻の声を聞いた。彼女は生きてるのか。殺人者特有の不安から、確かめずにいられないのだ、と。
これは半分当たっていたけれど(あくまで半分です)、翻訳の完成とともにある情事が裁判で裁かれることになり、女性が死に追いやられ、死んだはずの人が生きていたラストでは、スウェーデンでもこういうあざといドンデン返しが受けるの!?とびっくり。
この奇妙な話には翻弄されっぱなし。先を読むなんて小賢しい予測はまったく効かなかった。
一方、「そうだよね~、それしかないよね~」と予測が当たってちょっと小鼻が膨らんだのは「親愛なるアグネスへ」と「サマリアのタンポポ」の2編だ。
「親愛なるアグネスへ」は、昔親友同士だったアグネスとヘニィが再会、文通で昔の絆を取り戻すという友情譚。しかしヘニィが夫に愛人がいると書いてきたあたりから、どんどん不穏な方向に転がり始める。ヘニィは言う。愛人が誰かなんて興味がない、自分は夫が憎い、殺してやりたい、と。
ヘニィはアメリカの小説で読んだと言って(たぶんパトリシア・ハイスミスの『見知らぬ乗客』のこと)アグネスに交換殺人を持ちかける。当初はとんでもないと後ずさりしたアグネスだが、いまの家に住み続けたければ、遺産相続の権利を持つ亡夫の先妻の子らにある程度の金額を支払う必要があり、10万ユーロと引き換えに親友の頼みを受け入れる。殺人計画に、アグネスが官能的な喜びを覚えているのが、この話の行く末を見通す手がかりになる。
翻訳物は、訳者のあとがきも楽しみのひとつ。訳者の久山葉子さんはこの「親愛なるアグネスへ」が一番のお気に入りと書く。確かに女性同士の話って生理的にも理解しやすい。饒舌なセレブ妻ヘニィと大学教師であるアグネス。キャラクターに応じた書簡体の書き分けも巧みなら、手紙と手紙の間に、アグネスが過去のエピソードを回想で重ねていくプロセスもスリリング。滑らかさの中から飛び出す棘の鋭利さという意味では、これが一番かもしれない。
でも私が一番好きなのは、極端に短い「その件についてのすべての情報」。卒業式の直前、ひとりの女子生徒が交通事故(ひき逃げ)で亡くなる。彼女が取り組んでいたレポートに、代理教員をつとめる教師志望の大学生が点数をつけるという話だ。娘の死から立ち直れない両親の前で、もうこの世にいない彼女は最高得点をもらう。
この短篇には、市井の人々の感情や生活を書いたレイモンド・カーヴァーのにおいがちょっとある。訳者の久山さんは「何度読み返しても終わりのほうのシーンの不気味さに背筋がゾクリとする」と書いていて、私は意欲に燃えた溌剌とした魂が、ある出来事を通して内省する魂へと変化した瞬間を捉えた静かさに心打たれた。
ホーカン・ネッセルの文章は、説明が少ない。どこか行動主義のところがあって、登場人物の内面に潜り込むのをよしとしない。そのぶん、読み手の数だけ解釈が生まれるのだろう。もちろん原文と根気よく向き合った訳者の読みが正解だと思うが、感想が全然違うも面白い。
翻訳物には、読んだ後、誰かと話したくなるという人恋しさがついてきますね。

『悪意』
ホーカン・ネッセル 著、久山葉子 訳/東京創元社
“デュ・モーリアの騙りの妙、シーラッハの奥深さ、ディーヴァーのどんでん返し“と帯に書かれた、スウェーデンを代表するミステリー作家 ホーカン・ネッセルの傑作短編集。それぞれたっぷりと趣向が凝らされた5編が収録。週末にじつくりと取り組みたい1冊。ハリウッドでの映画化も予定されているそう。